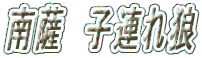 激シブの薩摩半島南端をディープ&チープに歩く (2003年5月1〜6日)
 指宿・東郷温泉にて |
|||
鰻池で静寂にひたる この日の朝も早くに目が覚めた。ニワトリが10羽くらい、休みなく鳴きまくっている。 「まつまえ」の隣にある「区営鰻温泉」が朝6時半からやっていると聞いたので、丘が寝ているうちに朝風呂へ。 まだ6時15分だったが、もう開いていた。外の番台のおばちゃんに200円を支払って入る。ここは脱衣室があった。  区営鰻温泉。まだ新しいが、木造の建物がグッドでごわす 区営鰻温泉。まだ新しいが、木造の建物がグッドでごわす中はタイル張りの小さな楕円形の浴槽が1つだけ。すでに地元のおっちゃんが入っていた。しばらくしてまた一人。鰻集落の人々が大切に使っている温泉のようだ。説明書きによると、崖崩れなどによって旧来の浴場がつぶれ、平成9年に新築したとのこと。湯は「まつまえ」同様やや熱めだが、すぐに慣れてくる感じ。 ところで、この集落にはツバメがやたらと多い。朝からそこらじゅうを飛び回っている。 「まつまえ」に着いたときも、「窓を開けるとツバメが入ってきてフンをしますから、網戸をしておいてくださいね」と言われたが、あらためて見ると、各家に3つずつくらい巣がくっついている。 「まつまえ」のおかみさんは毎年ツバメが来た日を記録し、その紙を柱に貼り付けている。それによると毎年だいたい3月中旬に来ているようだ。 部屋に戻ってパンを食い、起きてきた丘と支度をして、7時半ごろ出発。 区営鰻温泉の番台でソラマメを1袋200円(神戸のスーパーの3袋分以上の量)で売っていたので、1袋買ってスメでふかしてもらう。これを今日のおやつにしよう。 今日は外輪山を北側に越えて、再び指宿に出る予定。その前に、鰻池の湖畔に降りてみた。  朝の鰻池。地図で見ると完全な円形でごわす 朝の鰻池。地図で見ると完全な円形でごわす山川町の上水に利用されているらしく、ここも大切に管理されていた。ゴミの1つも落ちていない。 この湖畔にキャンプ場などを作ったら、鰻温泉にももっと観光客が来るだろう。しかし、そういう商業主義に迎合しないからこそ、ここが独特で静かな異空間であり続けているのだな。 それにしても、観光客の姿をまったく見ない。 「まつまえ」のおかみさんにゴールデンウイークの予約状況を尋ねると、「ぜんぜんなんですよ〜」とほがらかに笑っておられた。 「長期に逗留する湯治客なんかは来ませんか」 「最近はそういう人もいないですねえ。うちはオートバイのツーリングの人たちが多いです」 とのことだった。 静かで素朴な小宇宙を求めるあなた。鰻温泉はディープ&チープな穴場でごわすたい。 |
|||
薩摩つげで娘への愛を噛みしめる ソラマメ(甘〜い!)を食べながら、昨日降りてきた道を外輪山の尾根まで戻る。指宿方面(北)へ向かう道を探すが、見つけることができない。地図には点線の山道が書いてあるんだが・・・。 これかなと思って進むと、黒牛の牧場だった。薩摩といえば黒豚だが、牛も真っ黒だ。 エサをもらえると思ってか、牛舎の中に散らばっていた牛たちがいっせいに寄ってきて、サクぎわにズラーッと並んでこっちをじっと見つめる。丘が不気味がってあとずさり。 結局、山道を見つけるのはあきらめ、雑草をちぎって牧場のヤギに食べさせてから、昨日来た5kmの道を山川駅まで戻った。 今日目指すのは、指宿の沖合いに浮かぶ知林ヶ島(ちりんがしま)という小島。季節によって、1日のうち2〜3時間だけ砂州で本土とつながり、歩いて渡れるという不思議な島だ。それが今日の昼から2時半ごろまでつながるらしい。 丘は、「船の中の風呂」の次に、この島を楽しみにしていた。 1駅だけ汽車に乗って指宿で下車。ここから知林ヶ島への砂州の付け根まで、まっすぐ歩いて7kmくらい。でも時間があるので、またもや途中の温泉に寄っていくことにした。 駅を出てすぐ、そばの土産物屋に「薩摩ビール」を見つけた。ヴァイツェンとデュンケル。とりあえずヴァイツェンを1本買ってレジで栓を抜いてもらい、それをラッパ飲みしながら歩き出す。 おお、これはウマイ。地ビールのヴァイツェンはスカみたいなのも多いが、これは味も香りもしっかりとした、濃厚なる逸品じゃわい。いやー、ウマイウマイ。 と機嫌よく歩きつつ、じつは温泉の前にもう1ヵ所寄るところがあった。ガイドブックで見つけた、喜多つげ製作所というところ。薩摩つげのくしやブラシを作って売っている。 というのも、丘の妹のまりも(5歳)は、ものすごいちぢれっ毛だ。保育所100人中で文句なしのチャンピオンに輝いている。そのままだとアフロになるので、本人の強力な希望で毎朝ゴムで左右2つにくくっている。 が、ブラシでとかすたび、いちいち毛がひっかかって、「痛い!」と言っては涙をにじませる。かわいそー(だが、かわいい)。おまけに、サンタさんにもらった愛用のブラシがちょうど壊れてしまった。 で、出発前に、「指宿はつげの産地らしい。つげのブラシやったら静電気も起きへんし、とかしやすいかも」と言うと、まりもは「それを買ってきて」と言い、自分のおこづかいを僕に託したのだった。 1kmたらず歩いたところで、喜多つげ製作所を見つけた。だが表のドアはカギがかかっている。よく考えたら、ゴールデンウイークにこんな田舎の店が朝から開いてるはずがない。 でもよく見ると、ドアに張り紙がしてある。 「御用の方は、こちらにお電話ください」 さっそくケータイでその電話番号に電話してみると、「もしもし」とおばさんの声。 「今、喜多つげ製作所のお店の前にいるんですが、くしを見せていただけないかなーと思って」 「あ、そうですか、じゃあちょっとそのまま待っててください、すぐ2階の者が行きますから」 どうも店の2階に家族か従業員が住んでいるらしい。電話口のおばさんは別のところに住んでいるのだろう。 しばらく待っているとドアが開き、1才くらいの小さな女の子を抱いた若いお母さんが出てきた。 店に入ると、小さな喫茶店くらいのスペースが、徹底的につげのブラシとくしだらけ。センスよく陳列してあるが、本当につげのくし一本槍でやっている店だ。 さっそく「うちの5歳の娘が・・・」と事情を話すと、そのお母さんも、「えっ、じつはこの子の髪の毛も数ヶ月前まではすごかったんです〜」と、ひとしきり子どものちぢれっ毛ばなしに花が咲いた。 その子は、椿油をつけて毎日つげのくしでとかしていたら、髪がまっすぐになってきたのだという。「こうやってとかすんです〜」と実演してもらった。 全部手づくりなので、じっくり見ると1つ1つ微妙に形や値段が違う。持ってみると、とても軽い。でもしっかりと硬い。なるほど、これがつげか・・・。 で、薩摩つげのシンプルなブラシ(4000円)と、輸入つげのくし(900円)を購入した。薩摩つげは輸入もの(これも本つげだが)より色が濃く、より緻密な感じ。ブラシは歯が欠けたら修理してもらえるので、一生ものだ。 サービスで鹿児島産の椿油を1瓶つけてくださった。 途中で、「さっき電話を受けた者です〜」と言いながら、50代のおばさんが店に入って来た。頭にホットカーラーを巻きまくり、ヘヤーキャップをかぶったままだ。そんな状態で店に出るなっつーの。 「もうじき美しく完成するのよホッホホー」 「うわー、完成してからお会いしたかった〜」 しょーむないリアクションでウケた。 ともあれ、たった一人の客のために連休中にもかかわらず店を開け、ていねいに対応していただいて、丘ともども、なんだかほんわかした気分で店をあとにしたのだった。 喜多つげ製作所のつげブラシはこんなのです。 (僕がとった写真ではなく、どこかの物産展のHPです。左上の販売風景も喜多製作所ではありません。) |
|||
東郷温泉で仙人に出会う(・・・?) そこから10分ほど歩くと、前日に入った村之湯に出る。そのすぐ隣に東郷温泉があった。温泉が2軒、並んでいるのですぞみなさん。  東郷温泉。いい味だしてるでごわす。 弥次ヶ湯とはまったく違うおもむきの、南国情緒ただよう明るい外観だ。ピースフル・イージー・フィーリングな脱力系オーラを発散している。 隣の建物に窓口のようなものがあるが誰もいない。そこにある料金箱に大人250円、小人110円を入れて中に入ると、ここはいちおう脱衣所と浴室とが戸で隔てられていた。 さっそく服を脱いで浴室へ。  年季の入ったタイル張りの床が、温泉成分で真ッ茶色になっている。湯は熱めで、44〜45度くらいか。湯がすみっこからザバザバ流れ出ているが、どこから来ているのかなと思いつつとりあえず入ってみる。 すると、湯船の下は石敷きだった。んで、どうやらその下から湧き出しているようなのです。ドンジャラブクブクと。うひぇ〜い。 他の指宿の湯と同様、薄い塩味で、村之湯より少し白濁ぎみ。 奥には、ややぬるめの浴槽(この頁の頭にある楕円形の湯船写真がそれ)があったが、実際にはそっちも十分熱い。よく見ると、温泉が流れ込む部分に木の栓をして、流れ込む量を調節することで自然に冷ます仕組みなのだが、その栓が古くなって緩み、熱いのがドクドクと湯船に流れ込んでいた。 丘は洗面器に何杯か水をくんできて入れ、心持ちぬるくして、あとはがまんして入っていた。 先客は一人、色の白い、90歳は超えていそうな老人だった(上の写真にその背中とピンクの洗面器がチラリ)。黙々と、念入りに体を洗っておられる。無駄な肉のない、修行僧のような体だ。 温泉に浸かり、湯気越しに見るその白い背中はまるで仙人のようだった。 僕は瞬間的に何者かに操られるように合掌し、「オントバヤコウドアンバヤソワカ〜」と呪文をとなえた。すると老人の背中はみるみるうちに透明になり、やがてボン!という音がしたかと思うと、真っ白な煙が老人を包み、あっという間に煙ごと忽然と消えてしまった。 ・・・もちろんウソである。 ちなみに、鹿児島県には他にも「東郷温泉」がある。僕が「東郷温泉に行った」と言うと、ある人に「鹿児島の東郷温泉って、レジオネラ菌で死者が出たところでしょう?」と指摘された。 レジオネラ菌感染で問題になったのはこっちの東郷温泉だ(指宿ではなく薩摩郡東郷町にある)。ただしそこは設備のよさに地元では人気が高く、事件を機に循環をやめて掛け流しにするなど、管理を徹底して必死に汚名挽回の努力をしているらしい。あまり色眼鏡で見ないほうがよさそうな気がする。 指宿の東郷温泉はいうまでもなく源泉掛け流しのだだ流れであり、レジオネラ菌の心配は無用だ。(まあ僕ははじめからそんなもの気にしない主義だが) |
|||
「なのはな館」の異容に意気沈む 湯上がりほっこり。再びリュックを背負い、地図を見ながら幹線道路を避けて田舎道をゆく。 それにしても昨日に引き続き超快晴だ。すぐにじわじわと汗がにじんでくる。 河口に近い浅い川をのぞくと、青味がかったタイのような40〜50cmの魚がたくさん泳いでいる。ナイルティラピア(温泉地などで温水を利用して養殖されることがある)に似ているが、もしかして自然繁殖してるのか? 近くにいたおばさんにたずねてみたが、名前は知らないとのことだった。 半農村地帯を歩くうち、田畑の中に異様な巨大建造物が忽然と姿をあらわした。 丘が「なにあれ! ロボット?」と叫ぶ。 ウルトラセブンに出てきた地底探査ドリルマシーンみたいなのが斜め上を向いている。何十メートルもあるデカさ。しかもシルバーメタリックにまぶしく輝いている。 知らない人が見たら、まさにナントカ戦隊ナントカレンジャーに出てくる巨大バトルスーツか、宇宙基地かと思うだろう。 でもこれは指宿市の施設「ふれあいプラザ・なのはな館」だ。写真はとっていないので、まあこれをご覧いただきたい。 どうも、高齢者をおもな対象とする文化・研修施設のようだ。 しかしそれにしても・・・。 ひなびた温泉が点在するこの地に、このデザインで、このデカさで、この色調で、言うにこと欠いて「なのはな館」です・・・。 もしかしたら、この地域ではなにかと役立っている施設なのかもしれない。そのあたりは調べていないので、軽々に批判はしないでおこう。 しかしそれにしても・・・。 恐るべきセンスというほかない。 なんとなく指宿駅前のさみしげな表情を思い出してしまった。カネはここに叩き込まれていたか。 すばらしい芸術のような小温泉群が静かに湧き続けるこの地も、やはり日本の過疎地域に共通する深刻な問題からは自由でいられないらしい。 見たくないものを見てしまった。 「おとうさん、まだ着かへんの〜?」 湯上がりにじりじりと照りつける南国の太陽は、体力を容赦なく奪う。 暑いと思ったら、セミが鳴きまくっている。あの〜セミさん、5月3日なんですけど・・・。 1時間ほど歩いたろうか。海沿いに松林が広がるあたりに来ると、大きな観光ホテルがいくつか現れ、やがて広い芝生の広場に出た。じいさんばあさんたちがゲートボールに興じている。 「あーもうあかん、ひと休みしよ!」 大きな木の陰にへたりこみ、鰻温泉で買ったソラマメを全部食べ、神戸から持ってきたレーズンロール(リュックの中でぺしゃんこだった)も全部食べ、水筒の水も全部飲み干した。 木陰を渡る風が汗をひんやりとさましてゆく。体を横にしようとすると、丘が言う。 「あっ、あの堤防の向こう、海みたいやで! 見てきていい?」 さっきまでフラフラしてたくせに、さすがに子どもはこういうときには迷わず走る。 僕はそのまま横になり、しばらくゆっくり休憩してから堤防へ向かった。 堤防の向こう側は丘の言った通り、海だった。このあたりは錦江湾の入口だ。ずっと向こうの対岸に大隅半島の山々が並んでいる。 海岸線に沿って左のほうを見ると、これから向かう知林ヶ島が半分ほど見えている。 丘はリュックを背負ったまま波打ち際で砂山を作り、波の侵食で遊んでいた。堤防の上から声をかける。 「おうい、あそこやでー島は。そろそろ行こかー」 浜辺を歩くにつれ、知林ヶ島の全貌が見えてきた。本土の岬から、細い砂州がカーブしながら島に伸びているのがわかる。 「おい、もう砂の道でつながりかけてるみたいやぞ!」 歩みは自然に速くなる。まだ12時前だったが、けっこうたくさんの人たちが砂州へ向かって歩いていた。 |
|||
知林ヶ島で泣き濡れる 海中から姿をあらわしたばかりの砂州は、ゆるやかなS字状にくねりながら、島と九州本島との間を800メートルほどの長さで結んでいた。 不思議な光景だ。 砂州の付け根の岬まで来たが、全体像をデジカメに収めるには少し高いところへ登ったほうがよさそうだ。 ちょうどおあつらえ向きの場所に、展望台がおあつらえてある。高さ1.5メートルほどの木組みの低いものだが、せっかくだからこの上から撮影しよう。 ・・・でもその写真はありません。 展望台に登ってカメラを構えようとした瞬間、手がすべっちゃった。買ったばかりの中古デジカメちゃんは回転しながら展望台下の草地へ落下し、着地してバウンドした拍子に電池のフタが開いて、4本の単3乾電池が四方八方に弾け散った。 あわてて電池を拾い集め、セットしなおしてスイッチを入れてみる。 ・・・白い画面に、不吉な細い線が1本・・・。 どこをどうさわっても、不吉な1本の線以外のものが表示されることは、それ以後なかった(したがってこのあとの当旅行記には写真はありません。シクシク)。 も、もしかして、これまでに撮影した温泉なんかの写真も全部パーになったのかあ〜!!!!!??? 猛烈な脱力感が全身を襲う。 小さなカメラがちょっと故障しただけだ。なのに何なのだ、この頭の中が真っ白になるほどの空虚感、徒労感は・・・。 僕の落胆した様子を見て、丘までがしょげかえっている。 このとき僕は初めて気がついた。 この旅は当初、自分を見つめ直すためのストイックな一人旅を敢行する、との趣旨だった。しかし丘がついてくることになってストイックな一人旅計画は瓦解し、さらに生まれて初めてデジカメというものを手にしてしまった我々2人にとって、もはやこの旅は、 「パパとボクとのデジカメ撮影旅行」になり果てていたのだった! (スマヌ・・・こないだからさんざん予告してきた「悲しすぎる事件」とは、これだったのです) ま、知林ヶ島については指宿市のホームページもあるので、こちらをご覧いただければと。 丘とともにうなだれながら、気を取り直して砂洲に歩み出す。 するとその波打ち際に、たくさんの貝がらが打ち寄せられている。手にとってみると、いろんな形の、きれいで珍しい貝がいっぱいだ(写真がないのがつくづく残念)。ピラミッド型、キリ型、ホタテ型、タマゴ型、ホラガイ型・・・タカラガイもある。 干潮になって砂洲が現れるたび、黒潮に運ばれた貝がらがそのつど砂洲に供給されるのだな。拾ってポリ袋に入れてゆく。 砂洲の中ほどには、たくさんのクラゲや大きなヒトデなども取り残されている。 それらをつついたり海へ戻したりしながら歩くうち、島へ着いた。 島は潅木のブッシュに覆われ、中へ入る道もない。砂洲を歩いてきた人たちは、そのあたりで貝を掘ったりカニを捕まえたりの磯遊びをしている。 丘もリュックを背負ったまま、すぐにその輪に入って、貝掘りを試み始めた。 腰痛持ちの僕は貝掘りを自粛し、お茶を飲んで砂浜に寝そべった。 それにしても超快晴だ。南国の日差しはきつい。砂洲には日陰もない。 30分ほどして丘に声をかけ、九州本島に戻る。 喉が渇いてたまらない。国民休暇村の敷地内にある自動販売機にたどりつき、飲み物を買って、そのそばの芝生の木陰にへたりこんで横になったら、半時間ほど眠り込んでしまった(丘はその間、木登りをして遊んでいたらしい)。  デジカメは相変わらず線1本状態だったが、ためしにシャッターを押したら、昼寝した木陰からの景色が映っていたでごわす 目覚めて、用を足し、また歩き出す。 「パパとボクのデジカメ撮影旅行」も瓦解した今、もはや旅のコンセプトはひたすら歩くというストイックなものに回帰せざるを得ない。 試練の旅はここからが本番であった。 |
|||
殿様湯で薩摩藩士の怒りに触れる 徒歩の旅は、いかに車を避けて歩くかということに尽きる。 排気ガス発生機がブオンブオンと我が物顔に走りまくる幹線道路を歩いたって、楽しくもなんともない。だから多少遠回りになっても、細い生活道路や農道を選んで歩く。 目指すは、昨日最初に列車から降り立った二月田駅近くの殿様湯という温泉だ。そこまで約6km。その1kmほど手前には、うまそうなそば屋がガイドブックに載っていた。 魚見岳という低い山に沿って西へ歩く。 指宿というところは、水田はほとんど見当たらない。観葉植物やタバコなどの園芸作物の畑が多いが、何にも利用されていない、原野のような平地もけっこうある。減反政策の結果なのかもしれないが、3階建て住宅がビッシリ並ぶ神戸とは比ぶべくもない余裕の空間が広がっている。 ま、過疎地はどこもこういうものだが。建物は平屋建てが多い(台風対策か?)。 それにしても暑い。雲ひとつない南国晴れ。木陰にへたりこんでは水筒の水を2人で分けて飲む。 ふと気づくと、2人とも腕や首の後ろが真っ赤になっている。 「おい、これはマズイぞ、焼けすぎたら温泉に入られへんようになってまう」 こんなこともあろうかと、僕はTシャツ3枚のうち2枚は長袖を持ってきていた。道端で2人とも着替える。半そでしか持ってこなかった丘は大人サイズのブカブカだ。 2時に歩き始めて、かれこれ1時間。そば屋はまだか〜。 周囲は農家ばかりで、食べ物を売っているようなところはない。暑いし腹は減るし。 「あれ? おかしいな〜?」 細い抜け道を選んで歩いているうえ、ガイドブック付録の中途半端な地図しか持っていなかったせいで、なんか方角が狂ってきているような・・・。タバコ畑で農作業に精を出していたおばさんに聞くと、大きく北に逸れてしまっていた。 灼熱の日照りの中、畑の中をジグザグに歩いてやっと「小牧庵」というそば屋にたどりついたら、もう3時半だった。 中途半端な時間なのに、店は繁盛していた。地元の人気店らしい。 僕は看板の「小牧そば」を注文。ざるにあげた手打ちのざっくりしたそばに、さばの燻製でだしをとった味噌味の汁をかけて食べるという風変わりな一品。汁にごろごろ入っているさば身と、ミカンの皮の薬味とが不思議な風味を醸し出していて、まことにうまい。ビールとともに一気に胃袋に収納した。 丘は体が火照るあまり、ざるそばを頼んだ。普通の2玉分くらいの量があったが、このそばは素朴すぎて、ざるで食うには子どもにはやや不向きなようだった。結局、丘が残した分も食って、腹いっぱいなり。 ようやく人心地ついて再び歩く。線路を越えて川沿いに少し行くと、殿様湯に着いた。 ここはかつて島津の殿様が代々別荘を置いた場所だそうで、「文政10年(1828年)、第27代藩主・島津成興が湯殿を設けたのがはじまり」だとか。 時代が時代ならば僕などが入ったら即刻ハリツケ獄門に処されるはずの温泉も、今や大人250円、小人110円。よき時代に生まれたものよのう。 やや新しい民宿風の建物で、弥次ヶ湯や東郷温泉のようなひなびた雰囲気ではない。脱衣室と浴室が分かれていて、脱衣ロッカーもある。この旅7ヵ所目の温泉にして初めてロッカーというものに出会った。 タイル張りの浴室には、年季の入った楕円形の湯船が1つあって、湯がオーバーフローしている。一段高くなったところに島津の紋章が入った噴泉槽があり、そこから熱めの湯が湧き出して主浴槽に流れ込んでいた。薄い塩味、かすかに白濁と、指宿の他の温泉と似た泉質だ。 たっぷり漂う温泉の香りに包まれ、朝から歩き続けて疲れ切った足を湯に沈める。日焼けした腕や首筋はアチチだったが、じんわり〜と筋肉疲労が融解していく感触がなんとも心地よい。 すみっこには木の枕が置いてある。どうぞトドになってつかあさい、ということだ。さっそくお言葉に甘えて湯船のふちに横たわり、例によって洗面器で腹に湯をかける。 浴室には他に2〜3人の地元民の先客がいた。かくしゃくとした老人が40歳くらいの客と言葉を交わしている。 「わしゃ毎日ここへ入っとる」 「70超えて殿様湯入っとったら、もう殿様じゃね」 殿様じゃね、と持ち上げられて意気上がったのか、じいさまはおもむろに立ち上がると、一段高い島津マークの噴泉槽のへりに乗って休んでいた丘のところへ行き、 「ここに乗っちゃいかん!」 というような意味のことを鹿児島弁で言ったかと思うと、丘の手足を湯船のへりから払いのけた。丘は驚いて目を白黒させている。たしかにそこは飲泉もできる場所なのだが、別に丘は中に入っていたわけではないし、新鮮な熱い湯がじゃんじゃんあふれているので、へりに乗ったからといって湯が汚れるわけではないのだが。 さらにじいさまは、噴泉槽のへりに置いていた僕のタオルを取り上げ、 「×○△*○+$#・・・」(ヒアリング不能) と言って僕のほうへ投げ渡した。別にタオルが湯につかっていたわけでもないんだが。 じいさまは、源泉の清潔を守るというよりも、明らかに噴泉槽の「島津の紋章」を意識しているように感じられた。鹿児島の年寄りは今だに薩摩藩意識が抜けないという話を聞いたことがあるが、あるいはこれがその一端なのかもしれない。 じいさまに気圧された丘に「おとうさん、もう出よ」と促され、もうひとつかりだけして上がる。 自販機のジュースを買って飲みながら、ぶらぶらと二月田駅へと向かう。すでに夕方の5時前で、駅には下校途中の高校生がたくさんいた。 |
|||
くりや食堂&民宿で「日本一」に納得する 1時間に1本しかない列車が、ちょうどすぐに来た。1駅だけ乗って指宿駅で降りる。 この日泊まることになっていた宿はもう1駅先だが、その前に銀行に寄っておきたかった。所持金がちょいヤバイ感じ。 指宿に都銀はないが鹿児島銀行がある。たぶん都銀に入っている僕のカネもおろせるだろう。問題は、ゴールデンウイーク中でもキャッシュコーナーが開いているかどうかだな。5時を少し過ぎてしまっているが・・・。 鹿児島銀行はシャッターが閉まっていた。ちょうど帰ろうとしていた銀行員らしきおじさんを見つけて聞くと、明日もあさっても夕方5時までキャッシュコーナーは開いていると言う。 あ〜それさえわかれば一安心だ・・・。(この浅薄な判断がのちに悲劇を呼ぶことをこのとき知るよしもない) ホッとしてコンビニで買い物してから駅へ戻ったが、列車は例によって小一時間待たねばならない。時間つぶしに本屋やミヤゲ物屋へ寄り、またも薩摩ビールの今度はデュンケルを買って飲む。 うむ。深いロースト、しっかりした味。満足の逸品じゃのう。  デジカメを壊す前に撮っていた写真。JR九州は彩色センスがようごわす 列車で1駅の山川駅に着いたのは6時半前だった。前日はここから鰻池まで歩いたが、今日は駅すぐそばの「くりや旅館」という民宿を予約していた。 ここは「日本一安い民宿」を謳っている。1泊1580円〜(素泊まり)という、一瞬ひいてしまうような価格設定の宿だ。ただし、僕が電話した時点(1週間ほど前)で1580円部屋は満室とのことで、やむなく高いほうの新館2380円になった。 ただしここは小学生も同料金なので、合計すると前日の宿のほうが安くなる。 山川湾に面したくりや旅館は食堂も兼業している。カツオのタタキが名物らしく、連休ということもあってか猛烈に混んでいた。店の外まで並んでいる。ほかに外食できる店がないとはいえ、かなりの人気店のようだ。 宿泊受付も食堂のレジでやるので、お運びさんの手が空くまで少し待たねばならなかった。 別棟の部屋は新館というだけあって、ま新しい8畳間だった。ただし畳のサイズは前日の宿より小さめ。トイレ・洗面所は共同、風呂は温泉の共同浴場がある。テレビは100円コイン式。家族連れなどで満室のようだ。この値段としては十分満足できる。 一休みして、今夜はフンパツしてカツオのたたきでも食うか、と食堂へ行ってみたが、相変わらず混んでいるので、先に風呂に入ることにした。 2〜3人サイズの長方形の湯船が1つあるだけの、一見何の変哲もない風呂。だが、浴槽の蛇口をひねると、かなり熱い湯が勢いよくドバーと吹き出した。新鮮そのもの、プーンと香る、まったりとした食塩泉。これ、源泉そのままでっせ。 そのままじゃ熱いので水を加えて湯加減を調節するが、いやはやそれにしても贅沢なこっちゃ。源泉を好きなだけじゃんじゃか掛け流し。ウホホーイ。 さっぱりしたあとも食堂はまだ混んでいたが、なんとか席を見つけて座る。全席タタミの大広間式。 カツオのたたきは、いやーうまかった。量も多いし、さすがに産地だけあって新鮮そのもの。きざみニンニクとオニオンスライスがたっぷり乗っていて、ビールすすむすすむ。これで700円とは、そりゃ繁盛するわな。 他にもウナギ蒲焼やら焼肉やらいろいろたのみ、丘もたくさんガツガツ食って、3900円ほどだった。 くりや食堂&旅館、安いだけでないく内容もよろすい。日本の端っこで「日本一」を名乗るだけあるぞ! 満腹で部屋に戻り、丘とともにすぐ寝てしまった。 この日の万歩計:33080歩(約21.5km) |
|||
| 3日目へGO!→ |
|||
| ちょっとした旅<ホーム |